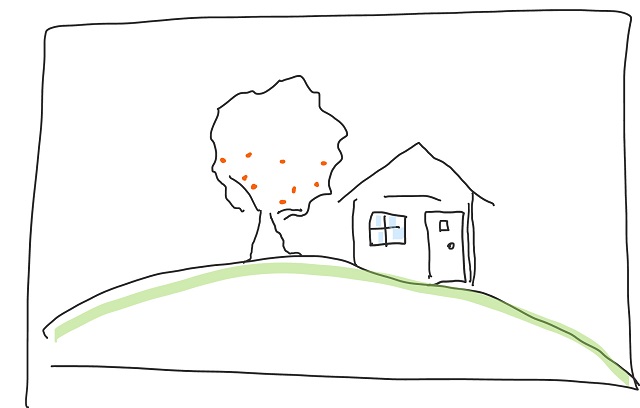約50年前の日本、高度成長期の住宅不足を背景にして怒涛のように建築された日本公団の団地群。特徴のひとつは、みーんな同じ間取り、のように見えること。でもよく眺めてみるとかなりバリエーションがあり、年を追って変化しているようです。けど、違いがわかんないなー、あんまり‥。ということで、そのあたりについては団地に詳しいサイト等があるでしょうからお任せしましょう。
建物配置については、さすがに場所が違えば団地ごとに異なります。建設時に敷地内残土をできる限り搬出しないように、元の敷地形状を活かした計画がなされたことは、以前に書いた通りです。とは言え、日照確保のために棟どうしが一定間隔を保ち、おまけに殆どが南向き配棟ですから、どれも同じに見えてしまうのは致し方ない。
そんな団地たち‥。後続の(そして今も続く)民間マンションとは明らかに一線を画す違いがあります。それは、敷地の大きさに対して圧倒的に建物(面積)が少ないこと。つまり現行で消化可能な容積率をかなり余らせた状態とも言えます(逆に1住戸あたりの土地持分が多いとも‥)。
航空写真(google mapなどでみてください)で比べてみれば一目瞭然です。マンションも戸建もぎっしりと並ぶ住宅地で、そこだけ縮尺が違うかのように住棟間隔が空いている敷地があります。学校のグラウンド‥ではありません、そこは団地の敷地。広い敷地に白い箱が点在し、箱の周りは大きく育った樹々の緑に占められています。
そんな団地のゆとりは、敷地や建物内に足を踏み入れてみると一層大きく感じられます。
この春も複数の団地でリフォーム工事を行いました。春先の日曜日、早朝に出向いたことがあります。低層階に位置するその住戸内に立つと、まだ低い太陽の光が何かに遮られることなく室内にサーッと差し込んでいました。バルコニーの先にはきれいに刈り込まれた広い芝生。更にその先には芽吹きを待つ樹々が連なっている。新緑はさぞ眩しいことでしょう。室内の反対方向を振り返ると、キッチンの窓いっぱいに咲く桜が‥(ちょうど満開だった)。そしてその静けさの中で、樹々を渡る鳥の繊細な声だけが響いている。ここは街と隣り合わせの桃源郷なのか‥。ちょっと言い過ぎですが、その時に感じたままを文章にするとそうなります。
そんなわけで、急ぎ立ち去るべきところ去り難く、暫しそこに佇んでおりました。
確かに団地の間取りや外観は、どれも同じく画一的に見えます。でもそんなこと、どーでも良いと思えるような豊かな時間と空間があるように思います。
さらに言うと、どの住戸も同一の白いキャンバスであるとしても、描かれる絵は十人十色であり、余白がたくさんあるということです。
上の写真は、文中に登場した住戸の完成直前の様子。この住戸の取得からリフォームまでご一緒したオーナーが考え、選び、自ら漆喰まで塗り上げました。素朴さと手作り感がありながら、断熱壁やインナーサッシを新設した快適な空間は、団地の豊かな環境を取り込んで唯一無二の住まいになったと思います。